-
 2022.07.26
2022.07.26介護コラム
介護福祉士としてキャリアアップするには?資格や給料について解説介護職で唯一の国家資格である介護福祉士。介護福祉士を取得した後もキャリアアップを目指したいと考える方も多いでしょう。この記事では、介護業界でのキャリアアップモデルを再確認し、介護福祉士でキャリアアップするための資格をご紹介します。 介護業界でのキャリアアップモデル 介護職のキャリアパスは、次の図のとおり整理することができます。 介護職員初任者研修が介護業界で働く上での、入門資格となります。その後、現場での経験を積みながら介護福祉士実務者研修を受講し、国家資格である介護福祉士の合格を目指すのが一般的です。 介護福祉士合格後は、介護の専門職として、さらなる経験を積み、介護福祉士の上位資格である認定介護福祉士を目指すことができます。また、ケアプランの作成等のマネジメント職に就きたい場合には、ケアマネジャー(介護支援専門員)を目指す方もいらっしゃいます。 介護福祉士がキャリアアップするための資格 介護福祉士合格後に、さらにキャリアアップを目指す方のための資格を3つご紹介します。 認定介護福祉士 認定介護福祉士は、介護福祉士の上位資格として2015年12月にできた民間資格で、介護人材のキャリアパスの中でも、最上位に位置づけられています。 利用者ニーズの多様化や高度化に対応するため、質の高い介護実践、介護職の指導・教育、医療職等との連携強化など、幅広い役割を担うことが期待されています。 認定介護福祉士を取得するためには、認定介護福祉士認証・認定機構が実施している認定介護福祉士養成研修を修了する必要があります。認定介護福祉士養成研修は、「認定介護福祉士養成研修Ⅰ類」と「認定介護福祉士養成研修Ⅱ類」で構成されます。 【受講要件】 ●認定護福祉士養成研修Ⅰ類 次の条件をいずれも満たす方 ・介護福祉士としての実務経験5年以上 ・現任研修を100時間以上受講していること ・レポート課題を提出もしくは、試験に合格すること。(現任研修を200時間以上受講し、機構が認める場合は免除) ●認定介護福祉士養成研修Ⅱ類 次の条件をいずれも満たす方 ・認定介護福祉士養成研修Ⅰ類を修了していること。 ・介護職の小チーム(ユニット等、5~10名の介護職によるサービス提供チーム)のリーダー (ユニットリーダー、サービス提供責任者等)としての実務経験を有すること 【受講時間数】 ・認定介護福祉士養成研修Ⅰ類 345時間 ・認定介護福祉士養成研修Ⅱ類 255時間 合計600時間 ※Ⅰ類を受講後、Ⅱ類を受講。 【試験】 試験はありません。 参考ページ:認定介護福祉士認証・認定機構 ケアマネジャー(介護支援専門員) ケアマネジャーとは、ケアプランを作成し、介護保険サービスの利用をサポートするプロフェッショナルで、正式名称は介護支援専門員といいます。 ご利用者やそのご家族がどのようなサービスを必要とされているのかのニーズを把握してケアプランを作成し、ご利用者が適切なサービスを受けられるように自治体や各事業所に依頼します。 これまでの介護職としての経験を活かしつつ、より大きな視点でご利用者のサポートをすることができます。 ケアマネジャーになるためには、各都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、さらに「介護支援専門員実務研修」の87時間を全て受講し、都道府県に登録申請をすることが必要です。 【受験要件】 次の条件をいずれも満たす方 ・特定の法定資格を有している方、もしくは生活相談員・支援相談員・相談支援専門員・主任相談支援員事務従事者 ・上記に基づく実務経験が5年以上かつ900日以上ある方 特定の法定資格とは? 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 【試験日】 10月の第2日曜日 【合格率】 23.3%(2021年試験) 【受験料】 12,800円 参考ページ:介護支援専門員都道府県別担当課一覧(公益財団法人社会福祉振興・試験センター) 参考ページ:令和4年度東京都介護支援専門員実務研修受講試験(公益財団法人東京都福祉保健財団) 社会福祉主事 社会福祉主事とは、都道府県や市町村等自治体の福祉事務所現業員(ケースワーカー)として任用される者に要求される資格(任用資格)です。社会福祉施設職員等の資格に準用されており、病院や介護施設で、ソーシャルワーカーや相談員として働いている方もいます。 社会福祉主事任用資格を持っている方が、公務員として自治体の福祉事務所に社会福祉主事として配属されることで、「社会福祉主事」として働くことができます。 【取得方法】 ・大学等において社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業する ・全社協中央福祉学院社会福祉主事資格認定通信課程または日本社会事業大学通信教育科を修了する(1年) ・指定養成機関を修了する(22科目1,500時間) ・都道府県等講習会を受講する(19科目279時間) ・社会福祉士、精神保健福祉士等を取得する 大学や短大を卒業されている方は、厚生労働省のホームページに掲載されている指定科目と、ご自身の卒業証明書に記載されている履修科目を確認してみると良いでしょう。実は指定の3科目を履修済だった(社会福祉主事任用資格を持っていた)ということも多いです。 参考ページ:社会福祉主事について(厚生労働省) ケアマネジャーの給料について 介護福祉士からキャリアアップするための資格を紹介しましたが、給与はどうなるのか気になると思います。認定介護福祉士については、まだ統計データがないため、ケアマネジャーの給与についてご紹介します。 令和2年の実態調査によると、介護福祉士の平均給与額が315,850円であるのに対して、ケアマネジャーの平均給与額は357,850円となっています。ケアマネジャーになることで、約4万円の給与アップが見込めます。 非常勤職員の平均給与額を見てみると、介護福祉士が196,630円に対して、ケアマネジャーは282,390円でとなっており、約9万円の差があります。 ケアマネジャーは、合格率から見ても、難易度の高い資格ではありますが、将来のことを考えるとぜひ取得しておきたい資格ですね。 参考:「令和2年度介護従業者処遇状況等調査結果」(厚生労働省) 介護職でキャリアアップを目指すなら三幸福祉カレッジ! 三幸福祉カレッジでは、介護職のキャリアアップに役立つ資格講座を実施しています。 先ほどご紹介したケアマネジャーの受験対策講座も開催しています。難易度の高い試験だからこそ、しっかりとした対策が必要です。三幸福祉カレッジのケアマネジャー受験対策講座は、長年の実績があり、専門のベテラン講師陣が毎年傾向を分析したオリジナルテキストで実施しています。通学コースはもちろん、いつでもどこでも学べる通信コースもご用意しています。 まずは、近くの教室を探してみましょう。 ▶︎介護職員初任者研修はこちら ▶︎介護福祉士実務者研修はこちら ▶︎介護福祉士受験対策講座はこちら ▶︎ケアマネジャー受験対策講座はこちら <無料説明会もオンラインで開催中!ご自宅から動画で視聴できます♪> ▶︎【無料】初任者研修オンライン説明会はこちら ▶︎【無料】実務者研修オンライン説明会はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら ▶︎【無料】ケアマネジャー受験対策講座無料オンライン講習会動画はこちら まとめ 介護人材のキャリアパスは、「介護職員初任者研修→介護福祉士実務者研修→介護福祉士」と一本化されている。 介護福祉士を取得した後のキャリアアップには、ケアマネジャーや認定介護福祉士を目指す道がある。 認定介護福祉士は、介護人材のキャリアパスの中では最上位として位置づけられている。 さらなるキャリアアップを目指すことで給与アップが見込める。 ▼各種SNSも実施しています。今回のようなお役立ち情報も定期的に更新しますので、ぜひご登録ください♪
続きを見る > -
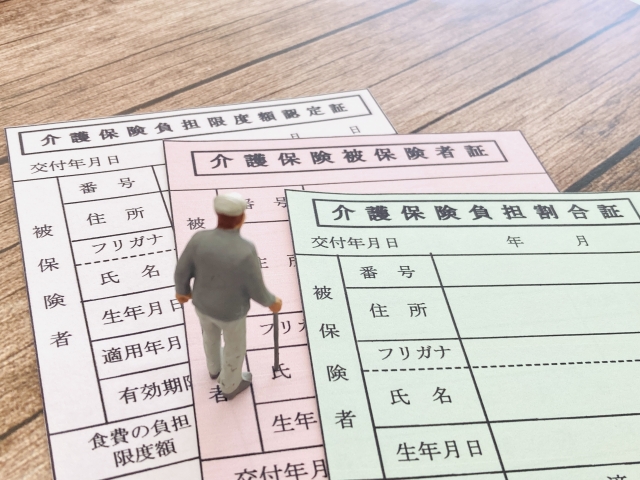 2022.07.20
2022.07.20介護コラム
要介護認定とは?認定基準や認定を受ける方法について解説親や自分が介護状態になった場合、どうしたら良いのかと考えたことがあるのではないでしょうか。 40歳になると自動的に介護保険の被保険者となります。そして介護保険に加入した人は、介護や支援が必要であると認定されると介護保険のサービスが利用できます。 しかし、介護保険サービスの利用方法を知らないために、介護状態を悪化させてしまったり、介護離職になってしまったりするケースが多いです。 いざという時のために、利用できる介護保険サービスを事前に知っておくことはとても重要です。 そこで今回は、身内や知人が介護認定を受けたという人のために、要介護認定を受ける方法や基準などを交え解説します。 要介護認定とは 介護保険制度では、介護保険サービスを利用したい被保険者が市区町村より「要介護認定」の判定を受け、その段階に応じたサービスを受ける仕組みになっています。 要介護認定とは、対象者の要介護状態がどの程度かの判定を行う重要な審査のことです。 要介護 要介護とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴をはじめ排泄や食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、原則6カ月(厚生労働省令が定める期間)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態のことを指します。 常時介護を必要とする状態については、判断基準が定められており、この基準に従って判断されます。 介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める要介護状態区分のいずれかに該当するものを要介護といいます。 要支援 要支援とは、身体上もしくは精神上の障害があるために、入浴をはじめ排泄や食事などの日常生活における基本的な動作の全部もしくは一部について、原則6カ月(厚生労働省令が定める期間)にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態を指します。 または身体上もしくは精神上の障害があるために、原則6カ月(厚生労働省令が定める期間)にわたり継続して、家事や身の回りの日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態のことです。 支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める要支援状態区分のいずれかに該当するものを要支援といいます。 引用:厚生労働省 要介護認定にかかる法令 要介護認定の基準 要介護認定の基準は、病気の数や症状の重さといった本人の状態そのものよりも、どれだけ介護に時間と手間を取られているかによって決まるのです。 介護の分類 要介護認定の結果は、日常生活能力に応じて、最も軽度な要支援1から重度の要介護5までの7段階と非該当に分類されます。 また区分によって受けることができる介護サービスの種類や時間が異なります。 ここからは、介護の分類による状態の違いについて見ていきましょう。 非該当(自立) 起き上がりや歩行などの日常生活上の基本的動作および薬の内服や電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力がある状態 要支援1 日常生活の能力は基本的にあるが、入浴などに一部の介助が必要な状態 要支援2 立ち上がりや歩行が不安定、排泄や入浴などで一部介助が必要であるが、適切なサービスの利用によって明らかな要介護状態に移行することを防ぐことができる可能性がある状態 要介護1 立ち上がりや歩行が不安定、排泄や入浴などで一部介助が必要な状態 要介護2 起き上がりが自力では困難、排泄や入浴などで一部または全介助が必要な状態 要介護3 起き上がりや寝返りが自力では困難、排泄や入浴、衣類の着脱などで全介助が必要な状態 要介護4 排泄や入浴、衣類の着脱など多くの行為で全面的介助が必要な状態 要介護5 生活全般について全面的介助が必要な状態 要介護認定等基準時間の分類 介護サービスの必要度の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピューターによる一次判定と主治医の意見書を基にした介護認定審査会での二次判定の2段階で行います。 コンピューターによる一次判定では、まず5つの分類に介護の手間を当てはめ、介護の手間を分単位の時間に算出することで、総合的に審査判定を行います。 5つの分類 直接生活介護・・・入浴、排泄、食事等の介護 間接生活介助・・・洗濯、掃除等の家事援助等 問題行動関連行為・・・徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 機能訓練関連行為・・・歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 医療関連行為・・・輸液の管理、褥瘡の処置等の診療の補助 要介護認定基準時間の分類 要支援1・・・上記5分類の要介護認定基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当する状態 要介護1・・・上記5分類の要介護認定基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態 要介護2・・・上記5分類の要介護認定基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当する状態 要介護3・・・上記5分類の要介護認定基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当する状態 要介護4・・・上記5分類の要介護認定基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当する状態 要介護5・・・上記5分類の要介護認定基準時間が110分以上またはこれに相当する状態 参考ページ:厚生労働省 要介護認定の仕組みと手順 要介護認定を受けるには 要介護認定を受ける前に、まずは居住地の各地区に設置されている地域包括支援センターで、介護保険の申請方法やどのようなサービスが利用できるかなど必要な情報を相談します。 そして地域包括支援センターに相談後、要介護認定を受ける申請手続きを要介護者の居住地の市区町村で行います。 申請には、65歳以上の人は介護保険被保険者証、40歳から64歳までの人は医療保険者の被保険者証が必要です。 その他、市区町村にある介護保険要介護認定・要支援認定申請書や、マイナンバーカードもしくは通知カード、印鑑、かかりつけ医がいる場合は主治医の意見書を持参します。 申請後は、自宅や入院先に市区町村の認定調査員が訪問し、介護サービスを受ける対象者の心身の状況を、本人や家族からヒアリングして調査します。そして介護認定審査会で認定調査の結果と主治医意見書をもとに、どのくらいの介護が必要かを判定します。 判定結果は、原則として30日以内に市区町村から通知が届くこととなっています。 参考ページ:厚生労働省 介護保険 サービス利用までの流れ まとめ 今回は、身内や知人が介護認定を受けたという人のために、要介護認定を受ける方法や基準などを交え解説しました。 要介護認定を受け介護保険サービスを上手に活用することは、身内や知人の介護状態を悪化させることなく、維持や改善することも可能になります。さらに、自身の介護による離職を防ぐことにつながりますので、介護が始まる前に介護保険制度をしっかりと知っておきましょう。 介護福祉士を目指すなら三幸福祉カレッジ! 三幸福祉カレッジでは、これから介護職を目指す方や、介護職としてキャリアアップしたい方のための講座を多数ご用意しております。 まずは近くの教室を探してみましょう! ▶︎初任者研修の詳細はこちら ▶︎実務者研修の詳細はこちら ▶︎介護福祉士受験対策講座の詳細はこちら ▶︎ケアマネジャー受験対策講座の詳細はこちら <無料説明会もオンラインで開催中!ご自宅からスマホで視聴できます♪> ▶︎【予約制】担当者に直接質問できる!オンライン説明会はこちら ▶︎【無料】初任者研修オンライン説明会動画はこちら ▶︎【無料】実務者研修オンライン説明会動画はこちら ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら ▶︎【無料】ケアマネジャー受験対策講座無料オンライン講習会動画はこちら ▼各種SNSも実施しています。今回のようなコラム記事を定期的に更新しますので、ぜひご登録ください♪
続きを見る > -
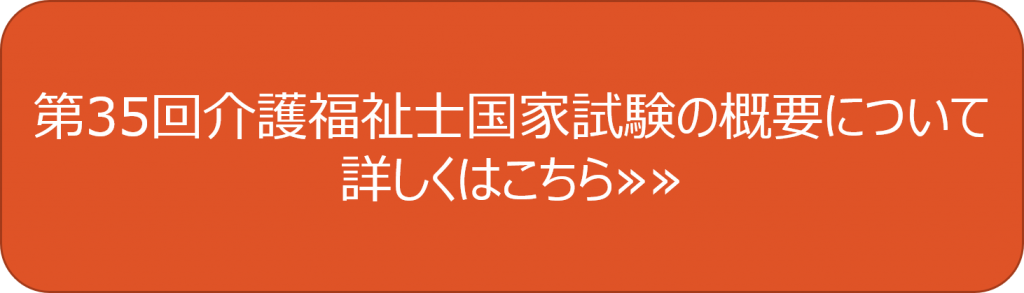 2022.07.20
2022.07.20試験情報
【介護福祉士】3分でわかる!第35回介護福祉士国家試験変更点 説明動画こんにちは。三幸福祉カレッジです。 第35回(2023年1月実施)介護福祉士国家試験は、出題基準が変更になりました。 ・どのように変更になったのか ・変更に伴う学習のポイントは何なのか 変更点を三幸福祉カレッジの講師が3分で説明します! おすすめの学習方法もご紹介しているので、ぜひご覧ください。 三幸福祉カレッジ講師 小林桂子 ▼介護福祉士国家試験の勉強方法やポイントをもっと詳しく知りたい方へ▼ 三幸福祉カレッジでは介護福祉士受験対策講座無料オンラインセミナーを実施中です! 自宅で、ご自身のパソコンやスマートフォンから気軽にご参加いただけます。 <こんな方にオススメ> ・第35回(令和4年度)試験に向けて、国家試験の概要・スケジュール・出題のポイントを知りたい ・介護福祉士国家試験に確実に合格したい ・仕事で忙しいので、効率よく勉強する方法を知りたい 一つでも当てはまった方は、合格に近づくチャンスです! 現役の介護福祉士講師が、試験のスケジュールから試験勉強のコツをわかりやすくお伝えします。 また、セミナーご参加の方は全員に、受講料の割引特典と合格するための秘訣が詰まった「合格の手引き」を無料プレゼントしています。 参加無料ですので、お気軽にご予約ください。
続きを見る > -
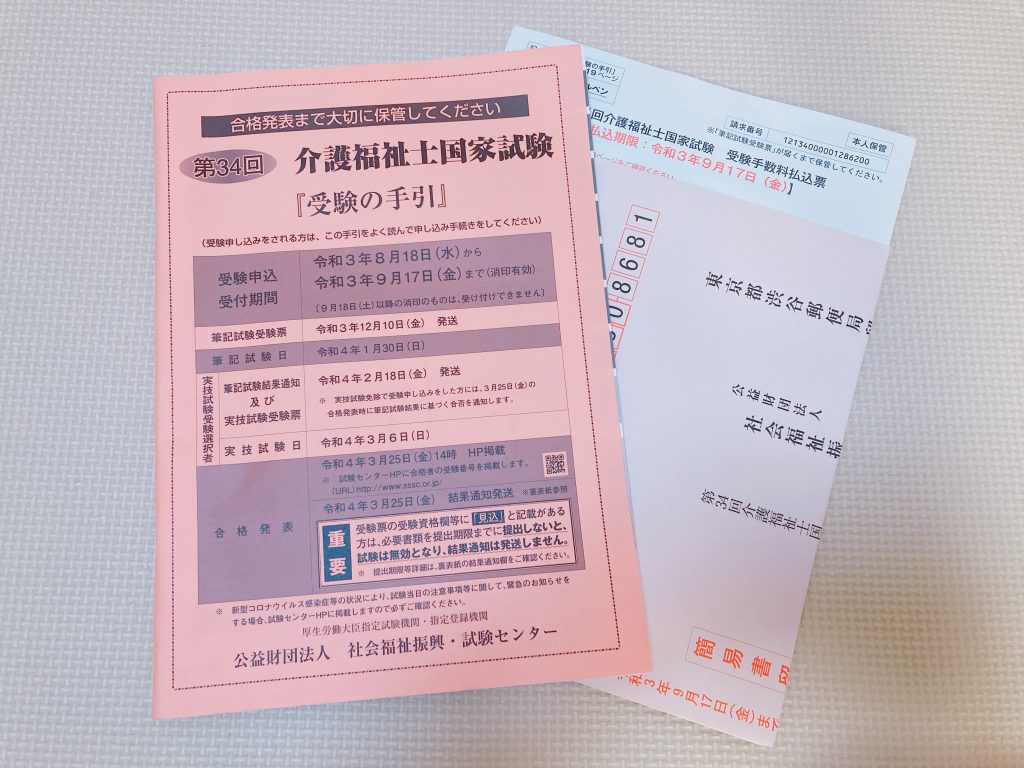 2022.07.01
2022.07.01試験情報
介護福祉士国家試験 (第35回・2023年1月実施) の「受験の手引」取寄スタート2023年1月に実施される「第35回(令和4年度)介護福祉士国家試験」の申し込みに必要な「受験の手引」の請求が始まりました。 ※画像は第34回介護福祉士受験の手引き 受験を希望する方は、あらかじめ自身で「受験の手引」を取り寄せ、2022年9月9日(金)までに受験申込書および必要な書類を郵送しなければなりません。 取り寄せ時期が遅れると、申し込みが間に合わず受験できなかった…ということにもなりかねませんので、「受験の手引」は早めに取り寄せ、余裕を持って準備しましょう。 受験申込書の受付期間 2022年8月10日(水)から9月9日(金)まで(消印有効) 試験センターページ(受験申込手続き) https://www.sssc.or.jp/kaigo/tetsuzuki.html 第35回(2023年1月実施)介護福祉士国家試験の概要 試験日時 1 試験日 筆記試験 2023年1月29日(日曜日) 実技試験 2023年3月5日(日曜日) 受験場所 筆記試験(35試験地) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 <注意事項> ・希望する筆記試験地1ヶ所を選択することができます(試験会場は選択できません) ・申込時に希望した「試験地」の変更はできません ・1試験地に受験者が集中し、受け入れできない場合は試験センターで他の試験地への振り替えを行う場合があります 実技試験(2試験地) 東京都、大阪府 第35回(2023年1月実施)受験者向け!介護福祉士受験対策講座無料オンラインセミナー 介護福祉士国家試験の試験概要から受験までのスケジュールを三幸福祉カレッジの講師が解説! ・受験までにどんな準備が必要なの? ・受験勉強のポイントって何? 国家試験受験に向けて少しでも不安がある方は、参加無料なのでぜひご参加ください。 無資格者もまだ間に合う!実務者研修のお申し込みはお済みですか? 第35回(2023年1月実施)の介護福祉士国家試験を受験するためには、実務者研修を8/31(水)までにお申込みする必要があります。 無資格の方もまだ間に合います! 介護福祉士国家試験の申込だけではなく、実務者研修のお申込みもお忘れなく。 介護福祉士国家試験の受験勉強の時間も確保するためには、8/31(水)までのお申込みがおすすめです。 満席クラスが続出しておりますので、お申込みはお早めに。 働きながら国家試験受験する方にオススメ!介護福祉士受験対策講座 三幸福祉カレッジでは、働きながら介護福祉士合格を目指す方が効率よく学習し合格するための、受験対策講座を誤用しております。 試験対策チームが最新の出題傾向を徹底的に分析して作成した「オリジナル教材」を使用しており、なんと2020年度の合格率は92.0%と全国平均を大きく上回る合格率でした! (※)全国平均71.0% 限られた学習時間で1点でも多く得点するためには、効率的な勉強方法とノウハウが凝縮された教材は欠かせません。 三幸福祉カレッジでは、ライフスタイルに合わせた通学・通信の豊富なコースを展開しております。 ぜひ一緒に介護福祉士国家試験の一発合格を目指しましょう! ▶︎三幸福祉カレッジ「介護福祉士受験対策講座」の詳細はこちら
続きを見る > -
 2022.07.01
2022.07.01その他
ホームページメンテナンス終了のお知らせお客様各位 日頃より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。 三幸福祉カレッジのホームページメンテナンスに伴い、一部ページが非表示となっておりましたが 本日メンテナンスが完了し、すべてのページをご覧いただけるようになっております。 お客様にはご不便をおかけしましたことお詫び申し上げます。 講座日程・教室の詳細や各講座の詳細につきましては、下記リンク先からもご確認いただけます。 【講座日程・教室検索】 https://www.sanko-fukushi.com/schedule/ 【講座詳細ページ】 ▼実務者研修 https://www.sanko-fukushi.com/course/jitsumu/ ▼初任者研修 https://www.sanko-fukushi.com/course/shoninsha/ ▼介護福祉士受験対策講座 https://www.sanko-fukushi.com/course/kaigofukushishi/ ▼ケアマネジャー受験対策講座 https://www.sanko-fukushi.com/course/caremanager/ ページの不具合により表示されず、閲覧できない場合はお手数をおかけいたしますが、下記にお電話くださいませ。 ▼お問い合わせ先 三幸福祉カレッジ ナビダイヤル 0570-015-350(平日8:50~18:00) 三幸福祉カレッジ
続きを見る >
MENU