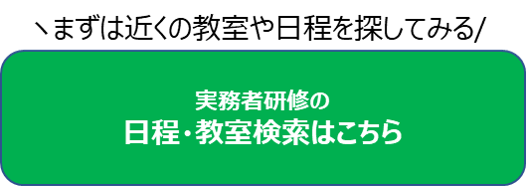介護コラム
実務者研修の費用は返ってくる?負担を軽減する3つの方法について
実務者研修の費用は返ってくる?負担を軽減する3つの方法について

実務者研修の受講を検討しているけれど、受講費用の負担に頭を悩ましている人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、実務者研修をお得に取得する方法を、国や自治体、各スクールで設けられている制度を交えて解説します。
この記事を最後まで読むことで、自分が活用できる実務者研修の費用負担軽減の方法を知ることができます。
目次
実務者研修にかかる費用

実務者研修にかかる費用は、受講する人が保有している資格や、受講するスクールによって異なります。
介護資格の無資格者が実務者研修を受講する場合は、8万円〜18万円程度が相場です。
介護資格の有資格者であっても受講料金に差があるのは、研修科目と受講時間数の違いです。
介護職員基礎研修の修了者は、研修科目は19科目と多岐にわたりますが、受講時間数は50時間と最も少なくなっています。
同じように、ヘルパー1級は18科目で95時間、ヘルパー2級は8科目で320時間、ヘルパー3級は3科目で420時間、初任者研修は9科目で320時間です。
そして、介護資格の無資格者は、研修科目は20科目で450時間と、当然のことながら最も多くなっています。

出典:厚生労働省「届出の必要ない研修にかかる修了認定科目について」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/care/dl/care_16.pdf
実務者研修の費用が返ってくるのはこんなとき

実務者研修の費用相場は、介護資格の無資格者や介護職員初任者研修の修了者で10万円程度です。
日々の生活もある中で、一度に10万円程度を支払うのは大きな負担です。
そこで、 実務者研修の費用を抑えることができる国や自治体で実施されている各種の免除や給付金の制度を上手に活用しましょう。
実務者研修を受講する際は一度に10万円程度を支払いますが、各種の制度を活用することで、条件を満たせば支払った費用の一部が返還されるケースがあります。
1. 国や自治体による費用の負担

国や自治体が費用を負担してくれる制度には、教育訓練給付金制度やひとり親支援事業があります。
また、各自治体ごとにさまざまな種類の免除や給付金の制度もあります。
ご自身が対象かどうかは、自治体やハローワークで確認することができます。また、スクールによって対応している給付金制度が異なるため、スクールのホームページを確認しましょう。
a. 教育訓練給付金制度
教育訓練給付金制度とは、働く人々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援する国の制度です。
雇用の安定と就職の促進を目的としており、厚生労働省が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されます。
給付金の対象となる教育訓練は、レベルなどに合わせて3種類あります。
【教育訓練給付金制度】
①専門実践教育訓練給付金制度
一定の条件を満たす雇用保険者のうち、受講修了後に受講料の50%が、受講修了後1年以内に就職・介護福祉士国家試験合格でさらに、20%(合わせて最大70%)が給付される。
②教育訓練給付金制度
一定の条件を満たす雇用保険者のうち、受講修了後に受講料の20%が給付される。
③特定一般教育訓練給付金制度
一定の条件を満たす雇用保険者のうち、受講修了後に受講料の40%(上限20万円)が給付される。
参考ページ:
厚生労働省「教育訓練給付制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
三幸福祉カレッジ 受講料が戻る給付金制度
https://www.sanko-fukushi.com/fee/#a4
b. ひとり親支援事業
ひとり親支援事業とは、母子家庭自立支援給付金および父子家庭自立支援給付金事業と呼ばれ、母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援する国の事業です。
対象教育訓練を修了した際に、受講費用の60%が支給されます。
母子家庭自立支援給付金および父子家庭自立支援給付金事業は、制度を設けていない都道府県等に居住されていない場合は、支給の対象とならないため、必ず事前に居住の市(町村在住の人は都道府県)に相談しましょう。
参考ページ:
厚生労働省「母子家庭自立支援給付金および父子家庭自立支援給付金事業の実施について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986.html
三幸福祉カレッジ 受講料が戻る給付金制度
https://www.sanko-fukushi.com/fee/#a4
c. 自治体ごとの制度
各自治体においても、実務者研修を取得するための支援制度があります。
例えば、東京都墨田区では、実務者研修受講料の助成事業を実施しています。
実務者研修の受講料やテキスト代、実習に要した費用等のうち、助成金の交付を受けようとする人が、当該研修を実施した機関へ支払った金額が対象で、7万円を上限に助成されます。
対象人数が各年度先着20名と少数であり、5つの条件を満たす人が対象です。
対象者の詳細や申請方法等は、墨田区のホームページで確認できます。
参考ページ:墨田区「実務者研修受講料の助成事業」https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/koureisya_kaigohoken/kaigo-jinzai-kakuo/jitumusya.html
お住まいの地域において、実務者研修の受講サポートが実施されているかを確認してみましょう。
2. 自治体からの貸付免除

自治体によっては、実務者研修の受講資金を貸付する制度を設けています。
東京都の例で言うと、介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度という名称で取得費用を支援しています。
貸付額は20万円以内で、実務者研修施設に払う授業料や実習費、教材費当の納付金のほか、参考図書や学用品、交通費や国家試験の受験手数料等の経費に充当可能です。
貸付期間は実務者研修施設の正規の修学期間で、無利子での貸付できます。
また、東京都内で介護福祉士として介護事業等に2年以上継続従事することで、実務者研修の費用を全額返還免除されるケースもあり、介護福祉士を目指す人にとっては充実した優遇制度といえます。
対象者や返還免除の条件などの詳細は、東京都福祉人材センターのホームページで確認できます。
参考ページ:東京都社会福祉協議会「介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度のご案内」https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/documents/R3jchirashi.pdf
対象者や貸付額、返還免除などは、各都道府県の社会福祉協議会によって異なるため、お住まいの地域で確認してみましょう。
3. ハローワークで費用を抑えて受講

ハローワークを活用して実務者研修の受講費用を抑えることもできます。
ハロートレーニングという名称で支援を実施しており、国が行っている支援のため原則受講料無料(テキスト代は自己負担)で、全国にあるハローワークの窓口から気軽に申し込みや相談が可能です。
ハロートレーニングには、雇用保険を受給している人向けの公共職業訓練(離職者訓練)と、雇用保険を受給していない人向けの求職者支援訓練の2種類があります。
ハロートレーニングを受講する人は、ハローワークや訓練実施機関が、積極的に就職支援を行います。
公共職業訓練では、一定の要件を満たすと、離職前の賃金に応じた基本手当のほか、受講手当として日額500円(上限あり)や通所手当(上限あり)などが支給されます。
また、求職者支援訓練では、一定の要件を満たすと、職業訓練受講給付金が月額10万円と通所手当が支給されます。
一定の要件とは、本人の収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月25万円以下、世帯全体の金融資産が300万円以下などを含めて全部で7つあります。
ハロートレーニングの詳細や要件については、厚生労働省のホームページで確認できます。
参考ページ:
厚生労働省「ハロートレーニング特設ホームページ」https://www.mhlw.go.jp/hellotraining/
厚生労働省「求職者支援制度のご案内」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
スクールの割引やキャンペーンの活用もあり

実務者研修を受講するスクールが実施している割引やキャンペーンなどを活用し、費用を抑えることも可能です。
初任者研修を取得している場合で1万円~3万円程度、無資格の場合でも2万円〜5万円程度安く受講できます。
また、初任者研修と同じスクールで実務者研修を受講する場合や、知人や家族などが同じスクールで介護資格を取得していた場合は、スクール独自の割引を活用できるケースもあります。
さらに、各スクールでさまざまなキャンペーンを用意していることもあるので、実務者研修の受講を検討しているスクールに気軽に問い合わせしてみましょう。
関連記事:「実務者研修はどこで受ける?スクール選びのポイントや取得の方法について」
https://www.sanko-fukushi.com/news/23700/
まとめ

今回は、実務者研修をお得に取得する方法を、国や自治体、各スクールで設けられている制度を交えて解説しました。
実務者研修を受講の際しては、 国や自治体による各種免除や給付金、貸付制度のほか、ハローワークの求職者支援やスクールの割引およびキャンペーンなど、さまざまなサポートが用意されています。
住んでいる地域によって活用できる制度も異なってきますので、自分で厚生労働省や社会福祉協議会、スクールなどに確認、相談しながら、お得に実務者研修を受講しましょう!