-
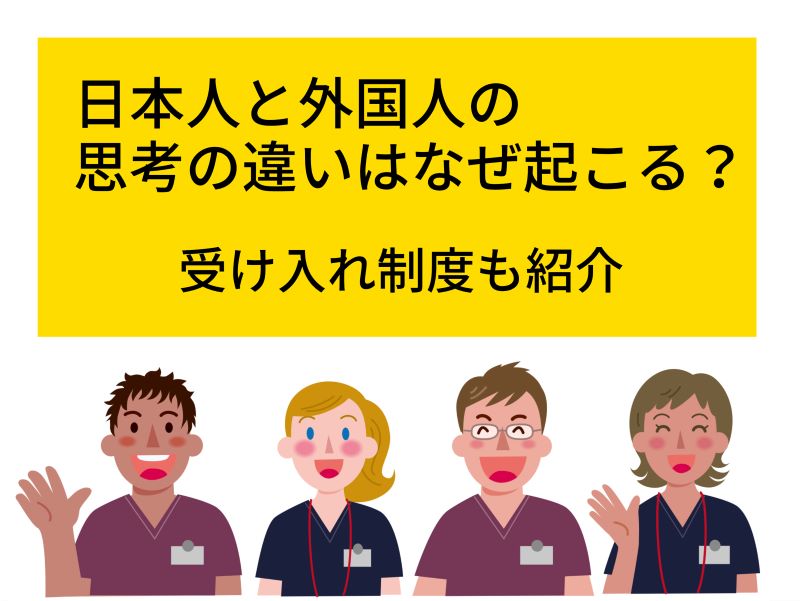 2023.06.30
2023.06.30介護コラム
日本人と外国人の思考の違いはなぜ起こる?受け入れ制度も紹介介護業界においても、外国人人材の活用が積極的に行われるようになりましたが、日本人と外国人の思考の違いによるコミュニケーションエラーなども発生しているようです。 この記事では、日本人と外国人の仕事に対する思考の違いについて解説し、一緒に働く際に工夫することについて考えます。 また、外国人人材の受け入れ制度は、複数ありますが、ここでは、EPA(経済連携協定)にフォーカスし、外国人の受け入れ制度についても紹介します。 1.EPAによるフィリピン・ベトナム・インドネシアからの受け入れ制度 EPAとは、特定の国や地域同士での貿易や投資を促進するための条約のことです。 介護分野では、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国との各協定に基づき、国家資格である介護福祉士を取得することを目的とした候補者の受け入れを実施しています。 外国人候補者は、送り出し国にて、6カ月間の訪日前日本語研修を受け、日本に入国後、さらに6カ月間の日本語研修を受けます。(ベトナムは、訪日前日本語研修12ヶ月間、訪日後日本語研修2.5か月間) その後、受入れ施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修に従事します。 4年目の介護福祉士国家試験で不合格だった場合は、一定の条件のもと、1年間の滞在延長ができます。 国家資格取得後は、希望者は在留資格「介護」に移行し、引き続き日本で働き続けることができます。 画像引用: EPA(経済連携協定)日本語予備教育事業 ─ 事業概要 ─ 日本の国家資格を取得してほしいという3国の期待が高く、受け入れ側の日本でも受け入れ施設による候補者の支援の強化や、国家試験の申請方法の見直し、再チャレンジ支援、介護職員の配置基準の見直しなどを行っています。 介護分野での受け入れの最大人数の上限は、1年につき各国300名となっており、令和3年度の実際のEPAでの入国者数は、インドネシア263名、フィリピン226名、ベトナム166名でした。 参考資料: 厚生労働省|インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて 関連記事▼(その他の受け入れ制度についてはこちらをご覧ください) 外国人介護人材の受け入れ制度について~受け入れ前に知っておくべき制度の基本~ 2.日本人と外国人の思考の違いが起こる理由 外国人へ指導を行う際、日本人への指導と同じようにしても、うまくいかない・・・という場面がありませんか。 日本人は世界的に見ても真面目で働きすぎだと言われています。日本人特有の仕事観は、外国人には理解しづらいでしょう。 外国人と一緒に働くにあたり、日本人と外国人の仕事への考え方の違いについて、知っておくとよいでしょう。もちろん個人差はありますが、一般的な仕事への考え方の違いについて紹介します。 理由1.外国人はプライベートを大事にする 外国人は、効率的な働き方やプライベートな活動に重きを置く傾向があると言われています。 日本でも、ワークライフバランスが重要視されるようになり、働き方の改革が進められていますが、仕事最優先という考え方があるのが現状です。職場によっては、残業することや、有給休暇を取らないことが、献身的な働き方だという考える人もいるでしょう。 このように、仕事最優先と考える日本人に対して、外国人は、仕事よりも家族やプライベートの優先順位が高いです。 EPA受け入れ対象のベトナム・フィリピン・インドネシア等のアジア各国も家族を最優先に考える傾向があります。 理由2.外国人は専門性を重視する 日本では、終身雇用の働き方が長く続いてきた背景から、ひとつの会社に長く貢献することが良いとされる考え方が残っています。 一方、海外では、専門性を重視し、即戦力となる人材が求められます。よい条件があれば転職するという考え方が一般的だと言われています。 理由3.外国人は意見をはっきりと伝える 日本では、秩序や関係性を重要視するため、相手にとって都合の悪いことを言う場合には、直接的な表現を避け、遠まわしな表現をすることがあります。 一方、外国人は意見をはっきりと伝えます。個人の意見を主張することもあります。日本人がよく使う暗黙の了解や遠回しの表現から察するということも、外国人にとっては理解しづらいでしょう。 3.外国人を受け入れるメリット 外国人を受け入れるメリットは、どのようなものがあるのでしょうか。 受け入れ制度によっても目的が異なりますが、ここでは、全体的なメリットを紹介します。 メリット1.グローバルな視点がプラスされる 外国人と一緒に働くことにより、多様な考え方や視点に触れることができます。また、相互理解を意識することにより、職場全体のコミュニケーションが円滑になることも期待できます。 また、日本における在留外国人の数は、296万1,969人万人で、増加傾向にあります(令和4年6月時点)。今後、ご利用者にもさまざまなルーツを持った方が増えてくるでしょう。グローバルな視点は、職員間のコミュニケーションだけでなく、利用者サービスにも活かされるはずです。 メリット2.人材不足が解消される 人材不足の解消のために、積極的に外国人人材を受け入れていこうという動きもあります。 介護福祉士の資格取得後は、在留資格「介護」(いわゆる介護ビザ)に移行し、永続的に日本で働き続けることもできます。家族の帯同も可能で、在留期間も制限なしで更新可能です。 また、日本で働きたいと考える外国人は、若い人材が多く、貴重な若い人材の確保も期待できるでしょう。 4.外国人労働者と働くための工夫 外国人労働者と働くためには、どのような工夫が必要なのでしょうか。先ほど説明した、仕事への違いを知った上で、工夫すべき点を紹介します。 工夫①文化や信仰等を理解して働きやすい環境を整える 文化や信仰、歴史的背景等は国によって異なるため、さまざまな配慮が必要です。 たとえば、日本人にとってはあまりなじみのない信仰ですが、フィリピン人の約90%がキリスト教で、日曜日には教会で礼拝し、毎日決められた時間にお祈りする習慣があります。ベトナム人の約80%は仏教徒です。また、インドネシア人の多くがイスラム教徒で、1日数回の礼拝があります。外国人にとっては、仕事よりも大事と考えられていることもありますので、礼拝の時間を認める等の配慮が必要となります。 外国人介護人材と一緒に働くためには、その人の文化や信仰、歴史的背景等を理解して、働きやすい環境を整えることが大切です。 工夫②業務内容をわかりやすくまとめる 具体的な業務内容を洗い出し、外国人でも理解できるようにわかりやすくまとめましょう。イラストや写真を活用するのも有効です。 また、介護はチームで働くため、情報共有の方法も含めて、仕事の進め方を具体的に伝えるようにしましょう。 工夫③介護用語を教える 介護職として働くためには、介護場面で使用する日本語も覚える必要があります。 外国人が介護用語を学習するための教材も用意されているので、うまく活用しながら、介護場面での語彙や声掛け表現などを教えましょう。その際には、写真やイラストを使うと有効です。 外国人を指導する際に、指摘が必要な場面も出てくるかと思いますが、国民性の違いにより、大勢の前で指摘されたり、怒られたりするのを嫌う人もいます。 人前で指摘するのではなく、1対1で落ち着いて説明するようにしましょう。 関連記事▼ 【介護の日本語】外国人への教え方のコツをわかりやすく解説 まとめ 日本人と外国人の思考の違いについて説明しました。 国民性の違いもありますが、性格や考え方は、一人ひとり違うため、個別に相互理解を深め、コミュニケーションをとることが重要です。 今後、ますます外国人人材が増えていくでしょう。外国人の受け入れを機会に、職場のコミュニケーションや体制を見直し、誰にとっても働きやすい職場を目指してみてはいかがでしょうか。
続きを見る > -
 2023.06.29
2023.06.29介護コラム
ボディメカニクス8原則とは?腰痛予防や身体の負担軽減のための基本姿勢の保ち方について解説!おすすめの動画も紹介ボディメカニクス8原則とは?腰痛予防や身体の負担軽減のための基本姿勢の保ち方について解説 介護の現場では、1日に数えきれないほどの介助姿勢をとるため、手や腰、膝などの痛みに悩まされている人も多いのではないでしょうか。 ご利用者の移乗や移動、身体介助を行う際は、ボディメカニクスを活用した正しい姿勢や技術の習得が重要です。 ボディメカニクスを理解し実践することで、介護技術の基本姿勢を正しく保つことができ、より効果的な介助が行えます。 そこで今回は、介護では欠かせないボディメカニクスについて、技術を習得するメリットや8つの原則、活用する際の注意点などを交え解説します。 1.ボディメカニクスとは ボディメカニクスは、人間の動作および姿勢に関わる体の骨格や関節、筋肉や内臓などの各部位に力学原理を応用した動き、動作、運動、姿勢保持のための技術のことです。 ボディメカニクスは、英語で「Body Mechanics」と書き、身体を表す「Body」と力学を表す「Mechanics」を融合させたもので、介護でいうボディメカニクスとは、 力学原理を活用して最小の労力で介護を行う技術です。 介護では、移乗介助のような身体部位を動かす動的作業姿勢と食事介助のような姿勢を保持して行う静的介助姿勢とがあり、姿勢に対する頭や胴体、手足などの位置は、介護の場面によって異なります。 また、人間の体は地球の重力の影響を受けていて、動作によってはそれにより身体の負担が増えることがあります。 ボディメカニクスの活用方法を知っておくことで、身体の負担を軽減しながら日頃の介護を行うことができるようになります。 参考文献:小川鑛一・北村京子(2016)『介護のためのボディメカニクス』.東京電機大学出版局. 2.ボディメカニクスを習得するメリット ボディメカニクスを習得することによって、介護を行う際の身体の動きや姿勢を最適化して負担を軽減し、ご利用者に安心感を与えます。 メリット1.介護者の負担が軽減される ボディメカニクスを正しく実践することで、介護者の身体への負担を最小限に抑えることができます。 また、適切な姿勢や動作を身につけることで、筋肉や関節への負担が分散され、ケガや疲労のリスクも低減されます。 さらに、介護の長時間労働や重労働において、体力や健康の維持にもつながるため、介護業界で長くキャリアを積むことも可能です。 メリット2.ご利用者に安心感を与える 正しい姿勢や技術を活用して介護を行うことで、姿勢の安定やスムーズな動作が可能になるため、ご利用者はケガや転倒の心配をせずに安心した介助を受けることができます。 また、介護者自身の自信や安定感がご利用者に伝わり、ご利用者との信頼関係を築くことにもつながっていきます。 3.ボディメカニクスの8原則とは ボディメカニクスには8つの原則があります。 ボディメカニクスの要素をより効果的に発揮するためには、細かい部分まで配慮することが重要です。 ①重心を保つ ご利用者の体を持ち上げたり移動させたりする際は、重心をできるだけ低く保つことを意識します。 一般的に重心を低く保つには、膝を曲げて腰を落とした姿勢ですが、骨盤の位置に注意が必要です。 日本人の場合、立った際に骨盤が後傾している人が多く、骨盤が後傾した状態のまま腰を落としても、効率的に力を発揮できません。 骨盤を立てた状態で、膝を曲げ腰を落とすことにより、重心を低く保てます。 ②足を適切な位置に配置する 足を適切な位置に配置し、安定したベースを確保します。 体を支えるための基礎であり、床面と接している部分を結んだ範囲を支持基底面積と言います。 介助に応じて、支持基底面積である足先を前後、左右、斜めといったように広げて安定した姿勢をとることが重要です。 また、ベッド上における移動介助の際には、足先だけではなく、ベッドに手をついたり膝を乗せたりする方法を取り入れることで支持基底面積が広がり、より安定した姿勢を確保できるとともに力を発揮しやすくなります。 ③中立姿勢を保つ ご利用者の体を持ち上げる際は、脊椎(背骨)を中立姿勢に保ちます。 体幹部がねじれてしまうと力を十分に発揮できず、脊柱に負担がかかって腰痛の原因になるため、動かす方向に向き合うように位置し、骨盤と肩のラインを平行に保つように動かします。 また、背筋が屈曲した状態で介助を行うことも腰痛の原因になるため、背筋を伸ばし、息を吐くときには腹部の外側に圧をかけて体幹部を支えるようにします。 ④身体の回転を最小限にする ご利用者の体を持ち上げたり移動させたりする際は、身体の回転を最小限に抑えます。 また、体の向きを変える際には、足を使って回転させます。 無理なひねりや回転は、腰や関節に負担をかけるだけでなく、ご利用者にも不快感を与えますので、できる限り前後移動を取り入れるなど、身体を大きく動かすことなく効率的な動作を心がけましょう。 ⑤身体の負担を分散させる ご利用者を移動や移乗させる際は、てこの原理を使って身体の負担を分散させます。 てこの原理を活用することで、小さい力で体を動かすことが可能です。 また、手や膝に支点を作ることで姿勢が安定し、体の一部にかかる負担を分散させることもできます。 ご利用者の体重や力も活用しながら、両手や両足を使って均等に力をかけることが重要です。 ⑥身体を使って力をかける 持っている力を十分に発揮するためには、身体を使って力をかけます。 手先や腕、腰だけの力に頼らず、腹筋や背筋などの体幹部をはじめ、大臀筋や大腿四頭筋、ハムストリングスなどの大きな筋肉を活用しましょう。 また、動かす方向に足先を向けて重心移動を行うことで、ご利用者の体を動かします。 その際、重力へ逆らうように体を持ち上げようとすると腰に過度な負担がかかりますので、大きな筋群を活用して持ち上げずに水平に引くようにします。 ⑦動作とリズムを保つ 動作はゆっくりと慎重に行い、無理なくスムーズなリズムを保ちます。 急いだり無駄な動きをしないように心がけることで、一連の動作がスムーズかつ連続的に行え、時間のロスを最小限に抑えることができます。 また、リズミカルな動きはご利用者に安心感を与え、作業の効率性も高めます。 介助の際は、無駄な力や無理な動作を避け、スムーズでリズムの良い動きを大切にしましょう。 ⑧自分の身体の制限を認識する 自分の身体の制限や能力を正確に認識し、無理な動作や負荷を避けます。 特に、自分よりも体重のあるご利用者を一度に動かそうとすると、全身に大きな負担がのしかかります。 リスクのある動作や持ち上げなどには注意し、自分の能力や体力を過信しすぎないことが大切です。 また、必要に応じて適切な支援具を活用したり周囲にいる仲間の協力を得たりして、安全かつ効率的な動作を行うよう心がけましょう。 参考文献:竹田幸司(2021)『からだを正しく使った移動・移乗技術』.中央法規. 4.ボディメカニクスを行う際の注意点 ボディメカニクスを行う際は、正しい姿勢や技術を習得した上で、ご利用者と密なコミュニケーションを取りながら、一人ひとりの身体状態やニーズに合わせて実践することが重要です。 注意点1:ご利用者とのコミュニケーションを図る ご利用者に安心して介助動作へ協力してもらえるように、コミュニケーションを図りながらご利用者の意思や状態を確認し、介護の手順や意図を伝えます。 ご利用者の声やフィードバックに敏感に対応し信頼関係を築いていくことで、ご利用者が安心して介助を受けることができるため、よりスムーズなボディメカニクスの実践が可能です。 注意点2:正しい姿勢や技術を習得する 誤った姿勢や動作は、ご利用者や介護者自身に損傷を引き起こす可能性があるため、正しい姿勢やしっかりとした技術を習得しましょう。 ボディメカニクスを介護に活用する際は、背筋を伸ばし、体重を均等にかけ、安定した姿勢を保つといったように、常に自身の姿勢に意識を向けることが大切です。 注意点3:ご利用者によって対応が異なる ご利用者の身体状態やニーズは一人ひとり異なるため、ご利用者に合わせたボディメカニクスを実践します。 特に、病気を患っていたり身体機能に制約があったりした場合、普段通りの介助を行うとケガや状態の悪化につながりますので、事前にご利用者個々の情報を把握してから介助を行いましょう。 ボディメカニクスのまとめ 今回は、介護では欠かせないボディメカニクスについて、技術を習得するメリットや8つの原則、活用する際の注意点などを交え解説しました。 介護でいうボディメカニクスとは、力学原理を活用して最小の労力で介護を行う技術です。 ボディメカニクスの正しい姿勢と技術を習得することで、介護者およびご利用者の身体的な負担の軽減につながり、安全かつ効果的なケアを提供できます。 ボディメカニクスを初めて聞いた。具体的にどんな動作なのかあんまりイメージがわかない方には、わかりやすく解説した動画もおすすめです。 ご自身の体の負担を軽減するため、ご利用者の安全を守るためにもぜひ活用してくださいね。
続きを見る > -
 2023.06.29
2023.06.29お得情報
【介護福祉士受験対策講座】お申込み特典が追加されました!(一部対象講座限定)こんにちは。三幸福祉カレッジ 試験対策チームです。 この度、介護福祉士受験対策講座の下記対象講座の受講生特典として、 2023年1月29日に実施された第35回介護福祉士国家試験分析資料に加え、 第35回介護福祉士国家試験の解説動画を受講生限定で公開いたしました。 ぜひ対象講座にお申込みいただき学習にお役立てください。 ▼お申込み対象講座 完全マスターコース/ポイント速習コース/筆記通信コース/Web学習コース 今回の特典について、YouTubeにて詳細を配信中! ぜひご覧ください。 三幸福祉カレッジ
続きを見る > -
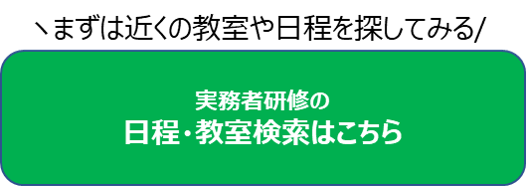 2023.06.03
2023.06.03試験情報
第36回(2024年1月実施)介護福祉士国家試験 試験情報第36回(2024年1月実施)介護福祉士国家試験 試験情報 第36回(2024年1月実施)介護福祉士国家試験の試験情報が試験センターのホームページにて公開されました。 筆記試験日は、令和6年1月28日(日)で、合格発表は令和6年3月25日(月)です。 国家試験の『受験の手引き』の請求は7月上旬より開始されます。 受験予定の方は、まずは試験概要を確認し、受験準備を進めましょう。 第36回(令和5年度)介護福祉士国家試験 試験概要(予定) 1 試験日 (1)筆記試験 令和6年1月28日(日曜日) (2)実技試験 令和6年3月3日(日曜日) 2 受験申し込み受付期間 令和5年8月9日(水曜日)から9月8日(金曜日)まで 3 合格発表日 令和6年3月25日(月曜日) 4 試験地 (1)筆記試験(35試験地) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 (2)実技試験(2試験地) 東京都、大阪府 参考:社会福祉振興・試験センター 関連ページ:【2022年最新】介護福祉士国家試験の難易度について解説!合格率は?受験条件は? 関連ページ:【第35回(令和4年度)】介護福祉士国家試験の難易度は?合格率や試験内容を紹介 介護福祉士国家試験受験~合格までの流れ 介護福祉士国家試験を受験するためには、実務経験ルートの方は、実務者研修の修了が必須です。 第36回の試験を受験するためには、2024年3月31日までに修了するクラスで受講する必要があります。 ≪合格までの流れ≫ 1.7月上旬~9月上旬頃:「受験の手引」の取り寄せ 試験センターのホームページから受験の手引きの取り寄せの手続きを行ってください。 試験センターはこちら 2.8月31日まで:実務者研修の申込み(三幸福祉カレッジの場合) 国家試験に間に合うクラスをお選びください。 締切が近づくと満席のクラスが増え、ご希望の教室で受講できない場合がありますので、お早めにお申し込みください。 3.8月上旬~9月上旬頃:受験願書の受付期間 「受験の手引き」を基に、介護福祉士国家試験の受験申込手続きを行ってください。 4.12月中旬:受験表到着 試験センターから受験表が届きます。手元に大事に保管しておきましょう。 5.実務者研修の受講・修了 2024年3月31日までに修了しましょう。 実務者研修は、自宅学習を提出する必要があります。受験勉強の時間も確保するためには、12月頃までには受講を終えておくことをおすすめします。 6.2024年1月28日(日):介護福祉士国家試験日 7.2024年3月25日(月曜日):合格発表 まとめ いよいよ、試験センターから試験概要が発表されました。 「受験勉強は久しぶり」「実務者研修の勉強と一緒にできるかな」という不安をお持ちの方も多いのではないのでしょうか。 三幸福祉カレッジは、働きながら介護福祉士国家試験を受験する皆様を応援しています。 実務者研修の受講や受験勉強のことお気軽にご相談ください。 三幸福祉カレッジ 0570-015-350(平日8:50~18:00)
続きを見る > -
 2023.06.02
2023.06.02その他
台風2号接近に伴う開講について日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 現在台風2号が接近しており、沖縄本島地方にかなり接近しています。 また、6月3日(土)にかけて、西日本から東日本の広い範囲で台風の影響を受けることが予想されます。 三幸福祉カレッジでは、各エリアの状況に応じて開講いたします。 各校の開講情報は各校ページにて随時更新いたしますので、ご確認をお願いいたします。 ●札幌校(北海道) https://www.sanko-fukushi.com/branch/sap/ ●仙台校(宮城県/青森県/岩手県/秋田県/山形県/福島県) https://www.sanko-fukushi.com/branch/sen/ ●高崎校(群馬県/栃木県/長野県/新潟県) https://www.sanko-fukushi.com/branch/tks/ ●東京校 (東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/山梨県) https://www.sanko-fukushi.com/branch/tky/ ●静岡校 (静岡県) https://www.sanko-fukushi.com/branch/siz/ ●名古屋校( 愛知県/岐阜県/三重県/富山県/石川県/福井県) https://www.sanko-fukushi.com/branch/nag/ ●大阪校 (兵庫県/大阪府/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県/広島県/岡山県/愛媛県/高知県/香川県/徳島県/山口県) https://www.sanko-fukushi.com/branch/osk/ ●福岡校 (福岡県/佐賀県/長崎県/大分県/熊本県/宮崎県/鹿児島県) https://www.sanko-fukushi.com/branch/fuk/ ●那覇校 (沖縄県) https://www.sanko-fukushi.com/branch/oki/ ご不明な点やご不安な点があれば、事務局までご連絡ください。 何卒宜しくお願い致します。 三幸福祉カレッジ 事務局 :0570-015-350 (平日 8:50~18:00)
続きを見る > -
 2023.06.01
2023.06.01お得情報
【受講料は当校が全額負担】初任者研修 就職応援制度三幸福祉カレッジでは、介護業界で就職・転職を目指す方のために、「就職応援制度」を実施しています。 就職応援制度とは 初任者研修の受講料を当校が全額負担します。 ①~③に該当する方がご利用いただけます。 <こんな方が就職応援制度の対象です> ①対象教室で初任者研修を受講される方 ②週3日(週20時間)以上働ける方 ③6ヶ月以内に勤務開始できる方 ご利用の流れ STEP1 WEBでお問い合わせ 下記の詳細ページよりお問い合わせください。 当校の担当者よりご連絡します。 STEP2 利用決定 お電話・対面(オンラインも可)で面談し対象条件に当てはまる場合初任者研修の受講クラスをご案内します。 ※残念ながら条件が合わなかった方も、受講料30%OFFで初任者研修をご受講いただくことができます。 STEP3 初任者研修の受講&就職活動 初任者研修の受講と並行して就職活動も行います。 ご自身が対象条件に当てはまるか不安な方も まずはお気軽にお問合せください。
続きを見る >
MENU