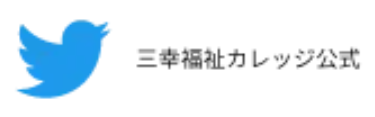介護コラム
介護を行うときに気をつけたいコミュニケーションについて

質の高い介護サービスを確保するためには、介護職員がより高度な介護技術を習得していることは欠かせません。さらに介護職員が利用者とのコミュニケーションを上手に取ることで、利用者のニーズを引き出し、的確な介護サービスの提供につながります。
そこで今回は、介護を行うときに気をつけたいコミュニケーションについて、コミュニケーションの種類やポイントを交えてご紹介します。
目次
介護におけるコミュニケーションの重要性
 人間はコミュニケーションを通して、心を通わせ、お互いに理解を深めます。
人間はコミュニケーションを通して、心を通わせ、お互いに理解を深めます。
介護においてより良い対人援助を行うためには、介護職員が利用者のことをよく知るとともに、自分自身のこともよく知ることが大切です。
利用者の希望や思いを把握し、信頼関係を構築できるよう、話をするだけでなく、利用者の話に耳を傾けるコミュニケーション技術を習得することが重要です。
コミュニケーションを行うときのポイント
 実際に利用者とコミュニケーションを取る場合、どのようなことを心がける必要があるのでしょうか。
実際に利用者とコミュニケーションを取る場合、どのようなことを心がける必要があるのでしょうか。
コミュニケーションを行うときのポイントを五つご紹介します。
ポイント1.答えやすい質問を心がける
二つや三つの単語で返答できる質問を心がけます。
例えば「寒くないですか?」「ご飯は好きですか?」など、「はい」や「いいえ」で返答できる質問は、短時間で状況を明確にできます。
また「何が好きですか?」「心配なことは何ですか?」など、内容や感想を尋ねる質問は、相手が自由に返答でき満足感も増します。
ポイント2.傾聴
相手の感情を理解し、受け止めながら話を聴きます。
利用者の多くは、考えていることや不安なことなどを聴いてほしいと思っているので、相手の言葉を妨げず親身になり、じっくりと耳を傾けて話を聴くことで信頼感が生まれます。
ポイント3.繰り返し確認
相手が話をする内容の中で重要な事柄を繰り返し、確認をします。
例えば「〜ということですね」と言うように確認することで、相手の話を理解していることが伝わります。
ポイント4.受容と共感
受容とは、相手の言葉や感情をありのまま受け入れることです。
また共感とは、相手の感情を受け止め、相手の立場になって理解し、その感情に寄り添うことです。
相手の価値観や人生観を大切にし共感することで、「気持ちを分かってくれた」と安心感につながります。
ポイント5.誠実さと礼儀
相手に対し尊敬の念を持ち、一つひとつのサービスを丁寧に提供します。
挨拶や敬語をはじめ、表情や態度には、相手に対する心が現れますので、常に誠実さと礼儀を大切にして接します。
参考ページ:介護ワーカー詳しく解説!介護のコミュニケーションで大切なこととは!?
コミュニケーションの種類

コミュニケーションには、言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションがあります。
二種類のコミュニケーションの特徴を理解し、組み合わせながら活用することで、お互いの信頼感はさらに増します。
言語的コミュニケーション
言語的コミュニケーションとは、相手に言葉や文字で伝えることで、筆談や手紙、メールなども含みます。
例えば、生活援助の際に「お手伝いしますが、よろしいですか?」と提供する内容を説明し、利用者から同意を得るのは言葉を使います。
また、利用者との間で介護サービスの契約を結ぶ際は、計画書に文字として記し、伝えます。
非言語的コミュニケーション
非言語コミュニケーションとは、表情や態度、身ぶり手ぶりで伝えることで、服装や口調、声のトーンやスキンシップなども含みます。
例えば、利用者と会話をする際に相手の手に自分の手を添えながら笑顔で話しかけたり、相手が話している際にうなずいたりなどがあります。
「目は口ほどにものを言う」というように、感情は言葉よりも表情に現れやすいです。
参考ページ:介護ワーカー詳しく解説!介護のコミュニケーションで大切なこととは!?
介護福祉士試験にも出題!
介護におけるコミュニケーションは、介護福祉士試験にも出題されており、 人間関係とコミュニケーションが2問、コミュニケーション技術が8問です。
人間関係とコミュニケーションは、コミュニケーション技術と関連性が高い科目ですので、関連させて勉強することがより効果的です。
ここでは、過去問題を交えご紹介します。
人間関係とコミュニケーション
よく出題される単語として以下の五つがあります。
- 自己覚知:自分の理想や価値観、感情などについて、客観的に理解すること
- ラポール:お互いに信頼し合い、心理的距離が縮まり、感情の交流を行うことができる状態のこと
- 受容:相手の言葉や感情をありのまま受け入れること
- 共感:相手の感情を受け止め、相手の立場になって理解し、その感情に寄り添うこと
- 傾聴:相手の感情を理解し、受け止めながら話を聴くこと
第33回(令和2年度)介護福祉士国家試験では、このように出題されました。
問題3 他者とのコミュニケーションを通した自己覚知として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 自己の弱みより強みを重視する
- 2 自己の感情の動きとその背景を洞察する
- 3 自己の行動を主観的に分析する
- 4 自己の私生活を打ち明ける
- 5 自己の価値観を他者に合わせる
答えは2です。
コミュニケーション技術
基本的な用語の理解やコミュニケーション技法を踏まえた事例問題などが出題されています。
第33回(令和2年度)介護福祉士国家試験では、このように出題されました。
問題30 Gさん(55歳・男性)は父親と2人で暮らしている。父親は週2回通所介護(デイサービス)を利用している。Gさんは、父親が夜に何度も起きるために睡眠不足となり、仕事でミスが続き退職を決意した。ある日、Gさんが介護福祉職に、「今後の生活が不安だ。通所介護(デイサービス)の利用をやめたいと考えている」と話した。Gさんが、「利用をやめたい」と言った背景にある理由を知るためのコミュニケーションとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 開かれた質問をする
- 2 「はい」「いいえ」で答えられる質問をする
- 3 介護福祉職のペースに合わせて話してもらう
- 4 事実と異なることは、訂正しながら聞く
- 5 相手が話したくないことは、推測して判断する
答えは1です。
まとめ

介護を行うときに気をつけたいコミュニケーションについて、コミュニケーションの種類やポイントを交えてご紹介しました。
コミュニケーションは、介護現場において必要不可欠であり、人間関係とコミュニケーションおよびコミュニケーション技術で学んだ知識は、介護実務や多職種との連携のときにも役立ちます。
介護福祉士を目指すなら三幸福祉カレッジ!
三幸福祉カレッジでは、これから介護職を目指す方や、介護職としてキャリアアップしたい方のための講座を多数ご用意しております。
まずは近くの教室を探してみましょう!
- ▶︎介護職員初任者研修の詳細はこちら
- ▶︎【無料】介護職員初任者研修オンライン説明会はこちら
- ▶︎介護職員初任者研修+実務者研修のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり)
- ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら
- ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら
- ▶︎【無料】実務者研修説明会動画はこちら