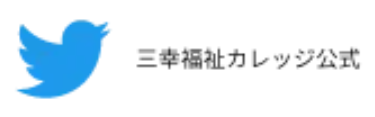介護コラム
認知症介護基礎研修とは〜介護職無資格者の研修義務化について解説〜

介護の無資格者であっても、訪問介護を除く特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設および通所介護において介護職として働くことは可能です。
しかし2021年度の介護報酬改定により認知症介護基礎研修の修了義務化が決定したことで、無資格で介護職として働くことができなくなります。
そこで今回は、認知症介護基礎研修について認知症ケアや義務化した背景を交えながらご紹介します。
目次
認知症介護基礎研修とは
 認知症介護基礎研修とは、認知症介護に携わる者が、その業務を遂行する上で基礎的な知識や技術と、それを実践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことを目的とした研修です。
認知症介護基礎研修とは、認知症介護に携わる者が、その業務を遂行する上で基礎的な知識や技術と、それを実践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことを目的とした研修です。
認知症ケアとは
認知症の人は、周囲から理解を得ることができず、人としての尊厳を失われていく状況に陥ることがあります。そのため認知症ケアにおいては、認知症の人も健常者と同じように尊厳が保持されることが大切です。
認知症の人の尊厳が保持されるための基本理念として以下のものがあります。
- 心のケア
- 関係性の重視
- 継続性と専門性の重要性
- 権利擁護の必要性
まず認知症の症状であることを理解し、認知症の人の気持ちを受け止めて寄り添うことが大切です。また認知症の人にとって環境の変化は大きな不安やストレスになるので、認知症の人の関係性を守ることを優先します。さらに認知症は進行性の病気のため、医療機関や専門的なサポートを利用しながら継続的なケアが重要です。
ただし認知症の症状であることを理解し対応することは難しいことです。介護職員や家族が認知症を理解し上手に向き合っていくための9大法則として以下のものがあります。
- 記憶障害に関する法則(周囲からは紛れもない事実でも、本人の認識からは消えていて事実でないことがある)
- 症状の出現強度に関する法則(家族や介護をサポートしてくれる人など、身近な人に対して認知症の症状がより強く出る)
- 自己有利の法則(自分に不利なことは認めず強情になり、自分の意見を貫き通そうとする)
- まだら症状の法則(認知症の症状が出たり出なかったりする)
- 感情残像の法則(起きた出来事に関する記憶は忘れても、感情だけはしばらく残り続ける)
- こだわりの法則(こだわりが強くなり他人の意見を受け入れなくなる)
- 作用・反作用の法則(うまく言葉で伝えることができなくても、周囲の反応を見て気持ちをくみ取ることができる)
- 認知症症状の了解可能性に関する法則(認知症の症状についてのすべてにおいて理解や説明ができるとされている)
- 衰弱の進行に関する法則(認知症の人は、認知症になっていない人より約3倍のスピードで老化する)
上記の9大法則を理解した上で認知症の人をケアしていくことが必要です。
参考ページ:介護のほんね「正しい認知症ケアとは|基本の考え方・家族が知っておきたい9大法則など
認知症介護基礎研修を義務化した背景
 認知症介護基礎研修を義務化した背景には、二つの理由があります。
認知症介護基礎研修を義務化した背景には、二つの理由があります。
- 2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になるとの推計から、今後も認知症の方の増加が見込まれ、あらゆる介護保険施設や事業所のスタッフが認知症介護の基礎的な知識を有している状況が必要である。
- 認知症介護に関する研修の体系上では介護職員初任者研修や無資格者を対象とした基礎的な研修がないため、介護サービス従事者向けの認知症ケアに関する基礎的な知識や技術、考え方などを修得できる機会を確保する。
中でも介護未経験や無資格の人が認知症への理解を深め、介護の質を向上させることが狙いです。
参考ページ:厚生労働省 「認知症施策推進総合戦略〜認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて〜」
参考ページ:厚生労働省 「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の概要」
認知症介護基礎研修の内容

2021年4月に認知症介護基礎研修が義務化されましたが、2024年3月までの3年間は経過措置として研修の受講は努力義務になっているため、現時点で無資格でも介護職として働くことは可能です。
また認知症介護基礎研修は認知症介護に関しての入り口の資格であり、認知症介護実践者研修や認知症介護実践リーダー研修などの上級資格へチャレンジもできます。
研修の対象者
認知症介護基礎研修の対象者は、介護保険施設や事業所などに従事する介護職員で、医療や福祉関係の資格を有さない無資格者です。
研修で学べること
認知症介護基礎研修では、認知症の人の理解と対応の基本や認知症ケアの実践の留意点を学ぶことができます。
具体的には、認知症の人を取り巻く現状や症状に関する基礎的な知識、認知症ケアの実践を行うために必要な方法について事例演習を通じて、背景や具体的な根拠を把握の上、ケアやコミュニケーションの内容を検討します。
研修にかかる日数と所要時間
認知症介護基礎研修は、講義3時間(認知症の人の理解と対応の基本)と演習3時間(認知症ケアの実践上の留意点)の合計6時間のため、1日で研修を修了できます。
研修を受講する方法
認知症介護基礎研修の受講方法は、主催する各自治体や委託された民間団体などによりeラーニングや集合型などさまざまですので、受講を希望する際は、該当する自治体などのホームページで確認が必要です。
また申し込みは、受講者個人ではなく、従事する介護保険施設や事業所の責任者を通じて行います。
介護職員初任者研修との違い

介護職員初任者研修は、介護の基礎から応用までを、一方の認知症介護基礎研修は、認知症介護の基礎となる知識や技術を学ぶことができます。
認知症介護基礎研修を受講することで、介護を必要とする人への対応が幅広く行えるようになるとともに、高齢者の約5人に1人が認知症になるといわれる2025年に向け、認知症ケアへの深い知識や技術を習得できます。
まとめ

認知症介護基礎研修について認知症ケアや義務化した背景を交えながらご紹介しました。
2021年4月の介護報酬改定に伴い、無資格者の介護職に認知症介護基礎研修の受講が義務化されました。
2024年3月までの経過措置期間に認知症介護基礎研修を受講しましょう。
介護職員を目指すなら三幸福祉カレッジ!
三幸福祉カレッジでは、これから介護職を目指す方や、介護職としてキャリアアップしたい方のための講座を多数ご用意しております。
まずは近くの教室を探してみましょう!
- ▶︎介護職員初任者研修の詳細はこちら
- ▶︎【無料】介護職員初任者研修オンライン説明会はこちら
- ▶︎介護職員初任者研修+実務者研修のセット講座はこちら(お得な受講料割引あり)
- ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座オンラインセミナーの予約はこちら
- ▶︎【無料】介護福祉士受験対策講座セミナー動画はこちら