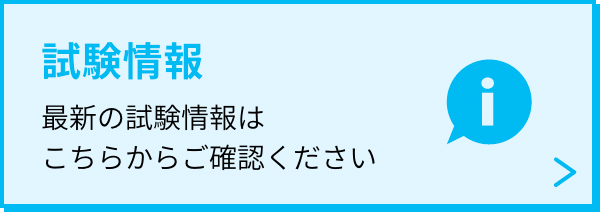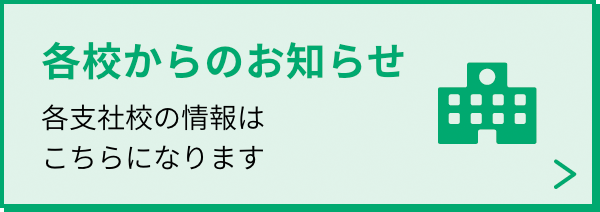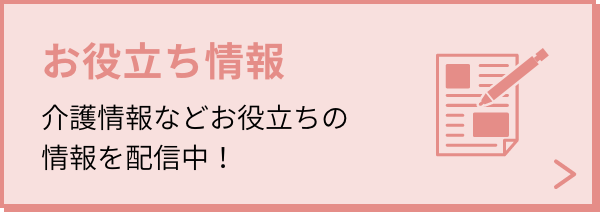お知らせ
- 2022.12.26お役立ち情報
- 【2022年度版】育児介護休業法の改正内容と押さえておきたいポイント
【2022年度版】育児介護休業法の改正内容と押さえておきたいポイント

デジタル化の急速な進展と新型コロナウイルス感染拡大により、働き方やライフスタイルが大きく変化しています。
人々の意識や価値観が変わる変革期の到来において、今回の育児介護休業法の改正は、近年でも特に多くの規則や運用の変更を伴う内容となっています。
企業の人事担当者や制度を利用する方も、「これまでの制度からどのように変わるのだろうか?」「自分も制度を利用できるのだろうか?」と疑問や不安を抱えているかと思います。
そこで今回は、育児介護休業法の改正について、詳しい内容やポイントを交えながら解説します。
育児介護休業法とは

育児介護休業法とは、 子の養育や家族の介護を行う労働者などの雇用の継続と再就職の促進を図り、仕事と家庭との両立を通じて、福祉の増進および経済と社会の発展に貢献することを目的とした法律です。
育児介護休業法で定められた支援には、以下のような制度があります。
・育児休業
労働者が、原則として1歳に満たない子を養育するための休業
・介護休業
労働者が、(いわゆる要介護状態)にある対象家族を介護するための休業
・出生時育児休業(産後パパ育休)
産後休業をしていない労働者が、原則として出生後8週間以内の子を養育するための休業
・子の看護休暇
小学校就学前にでの子を養育する労働者が、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気やけがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために休暇の取得が可能
・介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うために休暇の取得が可能
そのほかにも、所定労働時間の短縮等の措置や所定外労働の制限、時間外労働の制限や深夜業の制限などがあります。
※要介護状態とは、負傷や疾病又は身体上もしくは精神上の障がいにより、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。
1995年10月1日に、それまでの育児休業法が育児介護休業法に改められて以降、今日に至るまで様々な改正が行われてきました。

参考ページ:厚生労働省 「育児・介護休業法の改正経過」 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000136911.pdf
【2021年1月】介護休業制度の改正内容とポイント
2021年1月1日には、介護を行う労働者が、介護休暇を柔軟に取得できるよう、時間単位での休暇取得が可能になりました。
なお、子の看護休暇を取得する場合においても同様です。

法令では、いわゆる「中抜け」なしでの時間単位の休暇が求められています。
すでに「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇に変更することは、労働者にとって不利益な労働条件になるため注意が必要です。
※中抜けとは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることをいいます。
労働時間の端数は切り上げ
時間単位で介護休暇を取得する際の1日分の時間数は、1日の所定労働時間数としています。
1時間に満たない端数がある場合は、端数を切り上げます。
具体的には、1日の所定労働時間数が7時間30分の場合、8時間分の休暇で1日分の取得となります。

出典:厚生労働省「看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf
パートやアルバイトは平均所定労働時間数で計算
日によって所定労働時間数が異なる場合において、1日の所定労働時間数の定め方は、1年間における1日の平均所定労働時間数としています。
時間単位で介護休暇を取得する場合は、休暇を取得した時間数の合計が1日の平均所定労働時間数に相当する時間数になるごとに、1日分の休暇を取得したとして扱います。
なお、1日の平均所定労働時間数は、介護休暇1日の時間数の計算に用いるものです。

出典:厚生労働省「看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf
1日4時間以下の労働者の場合はどうなる?
2020年12月まで半日単位で介護休暇の取得ができなかった、1日の所定労働時間数が4時間以下の労働者の場合は、2021年1月から時間単位での休暇取得が可能になっています。
しかし、業務の性質や実施体制に照らし、1日未満の単位で休暇を取得することが困難と道められる業務に従事する労働者として労使協定を締結した場合、事業主側は、時間単位での休暇の取得を申し出を拒むことが可能です。
ただし、業務の態様に関わらず、一律に1日の所定労働時間数が4時間以下の労働者であることだけで、時間単位の休暇を取得する対象から除外することは適当ではありません。
参考ページ:厚生労働省「看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf
【2022年4月】介護休業制度の改正内容とポイント
2022年4月1日には、有期雇用労働者の介護休業取得要件の一つである「引き続き雇用された期間が1年以上である者」が削除されました。
これにより、無期雇用労働者と同様の扱いとなり、雇用形態に関わらず介護休業を取得しやすくなりました。

育児休業制度もさまざまな改正が行われている
育児休業制度についても、介護休業同様に様々な改正が行われています。
上記で解説した有期雇用労働者の取得要件の変更は、育児休業にも当てはまります。

この場合、パートやアルバイトなど、決められた期間だけ働く有期雇用労働者が育児休業を取得するのは、「引き続き雇用された期間が1年以上」「1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかではない」という要件があったため、育児休業の取得は認められない可能性が高かったのです。
しかし、2022年4月1日の育児介護休業法の改正により、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が撤廃されたことで、パートやアルバイトの方も正社員のような無期雇用労働者と同じように、入社直後から育児休業を取得できるようになりました。
2022年4月の育児休業制度改正
2022年4月1日における育児休業制度の改正では、上記で解説した有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和のほかに、雇用環境整備および個別周知、意向確認の措置が義務化されました。
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
事業主は、育児休業の申し出や取得が円滑に行われるようにするため、上記に記された雇用環境の整備のいずれかを選択して措置を講ずることが定められました。
妊娠や出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知、意向確認の措置

出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
労働者またはその配偶者が妊娠や出産したことなどを申し出たときは、事業者は個別の制度周知と意向確認の措置を講ずることが定められました。
2022年10月の育児休業制度改正
2022年10月1日における育児休業制度の改正では、産後パパ育児休業(出生時育児休業)が新設され、育児休業の分割取得が可能になりました。

出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
育児休業の分割取得において、取得回数が同じ子について原則として1回とされており、分割取得はできませんでした。
しかし、制度改正によって、取得が同じ子について原則として2回までの分割取得が可能になりました。
なお、産後パパ育児休業の取得回数は、この2回には含まれません。
事業主と労働者間での具体的な手続きの流れは、以下の通りです。

まとめ
今回は、育児介護休業法の改正について、詳しい内容やポイントを交えながら解説しました。
育児介護休業法は、時代の流れに沿って幾度となく改正されてきました。
2023年4月1日には、常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主は、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得状況として一定の内容を公表することが義務付けられます。
事業主と労働者の両者にとって今後もより良い職場環境となるよう、制度改正の内容を正確に把握しながら、就業規則を見直しましょう!
- アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年